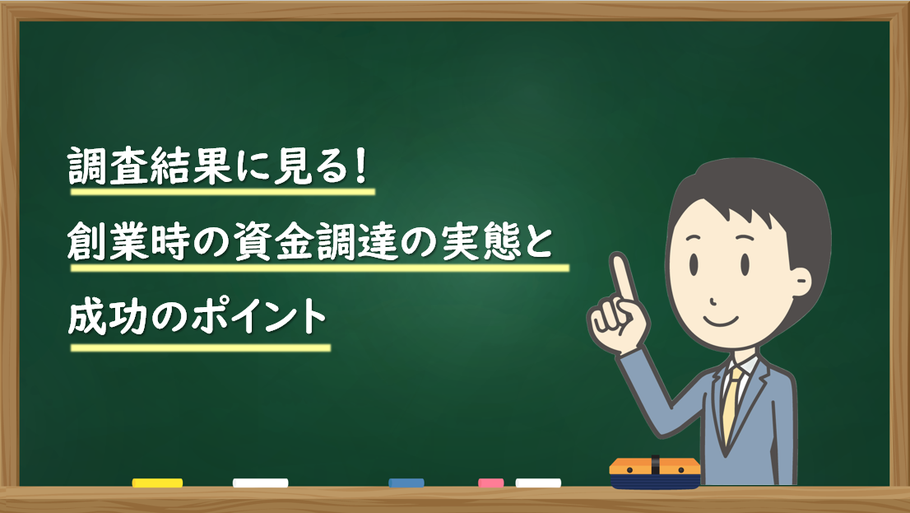
創業時の資金調達は、起業する上で大きな関門となります。
どこから資金を調達するかによって、以降の事業運営の可能性も大きく変わるためです。
日本政策金融公庫が行った調査によると、創業者の多くが融資のために準備をしており、その計画と戦略が重要であることが明らかになっています。
本記事では、創業時の資金調達の実態と、成功するためのポイントを解説します。また、資金調達の選択肢や創業計画書の重要点も合わせて紹介します。

「新規開業実態調査」とは、日本政策金融公庫総合研究所が、1991年度から毎年実施している調査で、開業者の属性や開業費用などのデータを時系列で比較している調査です。
この調査結果を紐解くことで、現在の開業者の実態やトレンドを理解し、より成功の可能性が高い資金調達を実現することができます。最新の調査資料は、日本政策金融公庫のHPに掲載されていますので、以下のリンクよりご確認ください。
「日本政策金融公庫 新規開業に関する調査」https://www.jfc.go.jp/n/findings/eb_findings.html
創業時の資金調達手段には、以下のような方法があります。
調査結果によると、開業時の資金調達額は平均1,197万円で、その資金調達先は、「金融機関等からの借り入れ」が平均780万円(平均調達額に占める割合は65.2%)、「自己資金」が平均293万円 (同24.5%)とのことです。
以上より、仮に融資を利用して開業を考える方は、自己資金と融資の割合が「1:3」の比率になるように準備するのが望ましいと言えます。
| 自己資金 |
創業時の資金の中核を担います。金融機関からの融資を受ける際にも、自己資金の比率が高いほど審査が有利になる。 |
| 日本政策金融公庫からの融資 |
政府系金融機関であり、創業者向けの融資制度が充実しているため、多くの起業家が活用。 |
| 民間金融機関からの融資 |
都市銀行や地方銀行、信用金庫などが提供する創業融資。審査基準が厳しく、信用情報や担保の有無が重要になります。 |
| 補助金・助成金の活用 |
国や自治体が提供する創業支援の補助金等を活用することで、自己資金を増やすことが可能。 |
| 投資家・VCによる支援 | 事業の成長が期待できる場合、投資家やベンチャーキャピタルからの出資を受けることも可能。 |
| クラウドファンディング | インターネット上で不特定多数の人々から資金を募る資金調達方法。BtoCのビジネスモデルでは検討の価値あり。 |
創業時の資金調達について、重要なポイントをまとめてみましょう。
まず、自己資金の準備が大切です。前述のとおり、創業資金の少なくとも4分の1は、自分で用意することが望ましいとされています。これにより、金融機関からの信頼を得やすくなると同時に、真剣に開業に向けて準備してきたことをアピールすることができます。
次に、創業計画書の作成に力を入れましょう。事業の将来性や収益計画を具体的に記載することで、融資審査を通りやすくなります。創業時は、金融機関に示せる事業の実績はありませんので、創業計画書は融資を受ける際の重要な判断材料となります。丁寧な作成を心掛けましょう。
最後に、融資の選択肢を広げることをおすすめします。公的融資だけでなく、民間融資や助成金など、複数の資金調達手段を組み合わせることで、リスクを分散できます。様々な選択肢を検討し、自分の事業に最適な資金調達方法を見つけましょう。
これらのポイントを押さえることで、創業時の資金調達をより確実なものにできるでしょう。

自己資金は、創業時の資金計画の基盤となります。
金融機関の融資審査では、自己資金の割合が大きいほど審査が通りやすくなります。
①貯蓄を活用する
日々の生活費を見直し、起業資金として積み立てることが重要です。
コツコツ貯めたお金ほど、開業への強い意志の裏付けとなり、審査上もプラスになります。
②退職金の活用
前職での退職金を創業資金として活用するケースも多くあります。
退職金はまとまったお金で用意できますので、開業に必要な資金を十分に賄える可能性が高いです。
③生命保険の解約、株式・投資信託等の売却
生命保険や株式・投資信託を自己資金として考える方も非常に多いです。
ただし、解約や売却をして口座に入金された状態でないと、開業に使える自己資金としてみなしてもらえないので注意が必要です。
④親族・知人からの出資
親族や知人からも資金調達をすることが可能です。ただし、返済する必要のあるお金の場合、自己資金として見てもらえない場合やトラブルに発展する可能性もありますので、十分に注意しましょう。
公的融資の代表例は、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」が考えられます。
創業者または創業間もない方が利用できる融資制度で、無担保・無保証での借入が可能ですので、非常に有利な融資制度です。
過去のブログで、日本政策金融公庫からの資金調達を成功させるポイントを詳しく解説していますので、ご覧ください。
日本政策金融公庫の他にも、民間の金融機関からの資金調達をすることも可能です。
特に、地域経済の発展を目的とする地方銀行や信用金庫・信用組合等では柔軟に対応してくれる可能性もあります。
また、自治体等と連携して有利な条件の公的融資制度を利用できる場合や、金利は高いもののスピーディーに資金調達できビジネスローン等も利用することが可能です。
こちらも過去のブログで、詳しく解説していますので、ご覧ください。

創業計画書では主に以下のような内容の記載が求められています。
| 事業の概要 |
どのような事業を行うのかを具体的に記載。 |
| 事業に関する経験・ノウハウ |
開業する事業に関連する経歴・資格等があれば記載する。 |
| ターゲット市場と競争優位性 |
顧客ターゲットや競合との差別化ポイントを明確にする。 |
| 収益計画と資金計画 |
事業の収支予測や必要資金をまとめた資金計画を現実的な数値で示す。 |
| 自己資金と資金調達計画 | 必要資金に対して、どのように資金を調達し、どのように活用するのかを記載 |
創業計画書作成におけるポイントは大きく以下の3つが挙げられます。
①具体的な数値を示す
売上や経費の予測を明確に記載します。その際には数値の根拠となる計算も記載するようにしましょう。
②論理的な構成を意識する
融資担当者が理解しやすいように整理し、一貫性のある内容での記載を心掛けましょう。
③審査の視点を考慮する
金融機関が求めるリスク回避策を説明する必要があります。例えば売上が計画を下回ったときの挽回策や資金繰り策なども検討しておくと、審査員の心証が良くなります。
より細かい創業計画書作成のポイントを過去のコラムでも紹介していますので、ぜひご覧ください。
創業時の資金調達にはさまざまな選択肢があり、成功するためには計画的な準備が不可欠です。
本記事で紹介したポイントを押さえ、自己資金の準備や創業計画書の作成を進めましょう。特に、日本政策金融公庫の融資制度は、多くの創業者にとって有力な資金調達手段となります。
しっかりと準備を進めることで、スムーズな創業と安定した事業運営を実現しましょう。
当事務所では、融資や補助金申請に関する無料相談を提供しています。専門家によるアドバイスを受けることで、融資の成功確率を高めることができます。オンライン相談は、初回のみ30分でご提供させていただきます。
現在考えている事業計画のブラッシュアップや資金調達の最適な方法を一緒に検討することができます。
「中小企業・個人事業者向け Zoom無料相談」はコチラ

~経営に関するお悩み事があればお気軽にご相談ください~
1,000社以上の支援経験のある代表が御社に最適なサポートをご提供いたします。